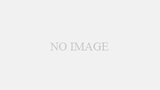シンプルライフを送る人には年賀状は必要か?不要か?
シンプルライフを送る人には年賀状は必要か?不要か?
これは大きな問題だ。いるといえばいるし、いらないといえばいらない。
必要と思う一つの原因は、事業をしている人であれば、顧客が去るのではないかという不安。個人なら、付き合いがなくなれば、困った時に助けてもらえないのではないか?という不安。
それと、こちらから年賀状を切るわけにはいかないという、義理がたい心。
年賀状が必要?不要?とも、両方もっともな考えであるので、ここでは必要か不要かの判断はしていない。
ただ参考までにこういう事例や考え方があるとだけいっておこう。
年賀状をださない超優良企業がある
たとえば「日本一“社員”が幸せな会社」ともいわれる未来工業では、年賀状はおろかお中元も禁止している。
会社自体も、コピー機は会社に1台きりのうえに、10枚コピーすれば、機械が自動的に止まるように改造していたりと、筋金入りの「ドケチ」ぶりだ。当然、お中元や年賀状も禁止。
未来工業は平均経常利益率10%以上を保つ、下手な大企業をしのぐ優良企業でもある。「日本一“社員”が幸せな会社」と呼ばれつつ、「儲かり続けている会社」でもある。
年賀状をださないとお客さんが去ると考える経営者はこんなケースもあると知っておこう。
もちろん未来工業は、商品の差別化という事をずっとし続けているから、これができる。そして昔からずっとこうしてきている訳だから、特別問題もない。
あなたの会社でこれを真似をして、影響がないとも言えない。そしてもちろん年賀状を急になくす事はできないかもしれない。
ただ一つの例として、年賀状を出さない優良企業もあるという事実を知っておくと良いだろうし、それをできるのが徹底した商品の差別化をしているからだという事実をしるのもいいだろう。
年賀状のプリンターに関わるコストが問題とする人が少なくない
多くの人が年賀状を出すのに躊躇する理由の一つが高すぎるコストだと思う。年賀状じたいがはがき代で52円かかってくる。
コレに対して、メールならほとんどタダで送ることができる。
多くの人は、はがき代は納得できるのだが、納得しにくいのは、印刷のコスト、とくに、プリンターのインクカートリッジのコストだと思う。
アマゾンでプリンターのカートリッジのレビューをみていると、高いという文句がとても多い。
それもそのはず、プリンターメーカーのビジネスモデルは、プリンターの価格を低価格で抑えて、インクカートリッジで儲けようというビジネスモデルだ。
プリンターが1万前後で買えるのに、なんでインクが数千円するんだ?っていう怒りだ。
そこのスキマに低価格で購入できる、格安インクが登場した。こういう事をされると儲からないプリンターメーカーは、格安インクメーカー相手に訴訟を起こした
キヤノンは2002年、東京都豊島区のリサイクル・アシストを特許侵害で提訴した。これは、キヤノン製の使用済みカートリッジに中国でインクを詰め替え輸入・販売しようとする行為が、特許を侵害しているとしたものである。2004年の一審判決でキヤノンが敗訴、2006年の二審ではキヤノンが逆転勝訴している。この他にも多くの裁判事例が発生している。
プリンターのインクをめぐっては、訴訟まで起きている。プリンターのインクが安ければ、こんなスキマ商売は産まれないし、アマゾンのレビューで文句もかかれない。
やはり多くの人がプリンターのインクは高すぎると感じているのだ。
純正インクを買わないことで生じるリスクとコスト
個人的な事をいえば、私はインクが高いのが嫌で、ほとんどプリンターを使わなかった。私も実際にプリンターメーカー純正ではない、格安インクを購入したことがある。
印刷回数は正直多くはない。ほとんどが年末の年賀状だった。年賀状の印刷のためだけにあるといってもいいほどだった。
この事が逆に災いしたのだと思う。インクが乾燥して、結果的にプリンターが使えなくなるという事態になってしまった。
最後には千円程度だした格安インクが全部カートリッジの掃除に使われて印刷できないという事態になってしまった。
これはインクの品質がわるいのか?プリンターが悪いのか?がよくわからない。
こうならないためには、月に2~3回は使っておいたほうが良いのかもしてない。
でも年に1回しか使わない消費者もいるだろう。そんな消費者は無視をしていいのか?
そもそもプリンターの洗浄にインクを使う意味がわからない。これではプリンターのインクを浪費させようと思っていると思われても仕方がないではないか?
取り外しができて、洗えるような手段は取れないのか?
1年に1回程度しか使わない場合、それで数年したら使えなくなるような品質にしておいていいのか?それがこの国の物作りなのか?
自分の無知は棚に上げて悪いのだが、このプリンターの一件で、プリンターメーカーも、インク業者も信用できなくなった。
純正を買わないから悪いのかもしれない、ただ純正を使ってもその多くが洗浄に使われるという事を経験した結果。安いインクに走ったという経緯もある。
なっとくできる値段で、十分にながく持っていれば、純正でも満足していた。
プリンターを買わなくても十分にやっていける時代になった
今はプリンターを持たなくても、USBにデータを入れ、コンビニにもっていけば、USBのデータを印刷する機能がついているコピー機もある。
写真印刷したければ、ネットで注文できるネットプリントという選択肢もある。
こんなことがあって、プリンターは無用なのではないかという意見も結構多い。
いまプリンターを維持していこうか?悩んでいる人がいるのなら、この辺の事も考えて行動されるといいだろう。
年賀状を格安で印刷してくれるサービスも多い
あと年賀状のみ印刷するのであれば、インターネットで年賀状のデザイン、文面、宛名書き、投稿まですべてやってくれるサービスもある。
上のようなサイトで安いサイトを探せば、リーズナブルに印刷ができる。コストの問題は多少は解決できるだろう。
わたしは最近プリンターを買い換えたが
ここまで書いておきながら、私の場合、家族が仕事でプリンターが必要になることがあるので、わたしは泣く泣く、スキャンなどの機能はまだ使えるプリンターを処分し、先日新しいプリンターを購入した。
以前のプリンターの痛い経験を通じて、以下のように運用することにした。
- 1ヶ月に1回~2回程度は印刷する。
- 半年から1年ぐらいがインクの寿命(必要経費)と思って諦める。
プリンターインクは半年ぐらいが寿命らしい。だから半年に1回は必要経費として考え購入することが必要なのだろう。
私は今後しばらくの間、毎年このプリンターインク税という強制的な徴収を受ける権利を得てしまった。とても納得できないが、仕方がないのだろう。
ただ、あなたの家族もプリンターを使わず、1年に1回年賀状印刷のためだけに購入しているのであれば、それはムダかもしれないので、プリンターを維持することの見直しをしたほうが良いかもしれない。
印刷はプロに回したほうが安くすむし、キレイにできる。スペースも浮くし、おまけにプリンターの維持費用もいらない。所有しなければ、環境負荷も少ないしね。
結論的に年賀状は必要か不要か?
年賀状が必要か不要か?は人によると思う。年賀状を出さないと決めた未来工業の考え方(商品の差別化は必要)はとても共感できる。
ただ個人的には、できれば出しておいたほうが良いような気がする。
私自信シンプルライフを追及しているし、世の中的にも、いろんなものを捨てる風潮になっているが、人の縁まで捨てる必要はないと思うのだ。
年賀状だけのやりとりというのは、あまり機能していない人間関係なのかもしれない。しかし機能していないからといって、すべてを切ってしまって良いのだろうか?
年賀状を出したくない機能不全の関係や、腐れ縁だって、なにか必要であるのから縁があったのかもしれない。
歳のせいかもしれないが、そう最近は思うようになってきた。そう考えるともう少し大切にしてみようと思うようになってきた。
もし年賀状をだすのが、費用面で負担があるようなら、上で紹介したような方法があるわけだし、年賀状を考えるのを機会に人間関係について、もういちど考え直したほうがいいのかもしれない。
年賀状を辞める派には、本当に必要な人間関係なんて多くはない、という意見ももちろんあるのだが、2軍だった人間関係が突然1軍になることもあるわけで、ちょっとこれは難しい問題だ。
もし費用がかさまないのなら、出してもいいと考えているなら、節約して出したほうがいいだろう。人間関係を切りたいと考えているのなら、出さないほうがいいだろう。
それが選ぶコツだと思う。それこそ死ぬ間際、年賀状に関して、どう考えるか?イメージしてみると良いだろう。
シンプルライフもミニマリストも、生き方の一つの方向性で、今後こういうのが主流になってくるのだと思う。
そんな事はないだろうと思ってはいるが、シンプルライフもミニマリストも、もしかして、たんなる一過性の流行かもしれない。
あとシンプルライフもミニマリストも過渡期で、今後どういう流れになってくるかわからないとこもある。10年後やっぱり年賀状を出すのが良いという時になって、再度出すのも出しにくい。
ミニマリストを送っているあの人が出していないから、ミニマリストのあの人は出していないからじゃなくて、自分はどうなのか?年賀状をただの紙切れとイメージするのではなく、人との縁と考えて見てみると、またすこし違ってくるのかもしれない。